ウェビナーノウハウ
ウェビナーでアンケートが重要な理由と効果的な実施方法を解説
最終更新日:2022/06/28
非対面のウェビナーは、参加者から直接のフィードバックが得られません。アンケートを実施することで、思いがけないニーズや大きな課題が見えてくることもあるでしょう。回答率を上げる方法や参加者に負担を掛けない設問の作り方を解説します。
目次
アンケートで重要な情報を得よう
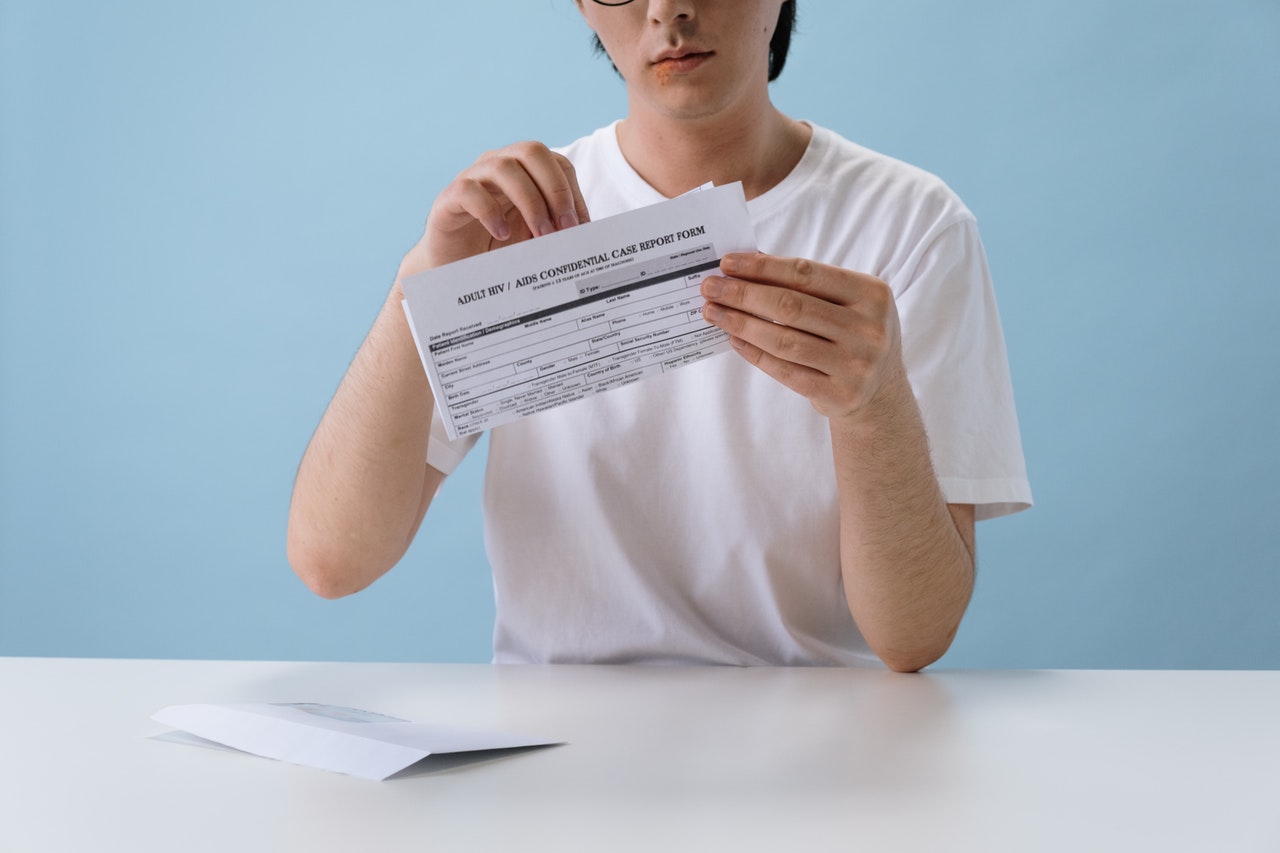
(出典) pexels.com[/caption]
多くのセミナーでは開始前や開始後に『アンケート』を実施します。参加者の顧客情報やニーズが把握できるアンケートは企業のマーケティング活動において欠かせません。
参加者のニーズを把握できる
アンケートの実施により、『参加者のニーズ』が的確に把握できるようになります。多くの企業は自社商品やサービスを多くの人に購入・利用してもらいたいと考えていますが、顧客の真のニーズが明確でなければ効果的なアプローチができません。
ウェビナー参加者の多くは、サービスや商品に多少なりとも興味を抱いている『見込み客』です。企業はこれらの見込み客を『顧客』へと育てる必要があります。
アンケートで取得した顧客データや感想は、企業の営業活動に活用できます。例えば、参加者のニーズに近い情報をメールや広告でタイミングよく送信すれば、サービス利用や次のウェビナー参加につながる可能性があるでしょう。
ウェビナーの改善ができる
初めてのウェビナーでは、人が集まらなかったり、途中で退席する人がいたりして、思うような結果が得られないものです。
ウェビナー前に『参加希望日時』のアンケートを実施すると、もっとも集客が見込める日時に開催日を設定できます。参加目的・質問事項・職業なども事前に把握できれば、参加者の意に沿った有意義な情報が届けられるでしょう。
また、参加者を増やすためには、回数を追うごとに内容に磨きを掛ける必要があります。アンケートで得た『改善点』や『要望』を次のウェビナーに反映できれば、ファンは徐々に増えていくでしょう。
アンケート依頼のタイミング

(出典) pixabay.com[/caption]
アンケートのタイミングは、ウェビナーの『開始前』『途中』『開始後』の3パターンです。アンケートの目的や質問の内容によって、適切なタイミングが異なります。
セミナーが始まる前に依頼
主催者の中には、「ウェビナーの詳細が決まってから集客を行うべきだ」と考える人がいますが、最初に大枠だけを決め、アンケート実施後に具体的な内容に落とし込んでいくというパターンもあります。
ウェビナー開催前に『個人の属性(職業・年齢・性別・居住地など)』『参加動機』『ウェビナーへの要望』などが収集できると、参加者のニーズに合致した満足度の高いコンテンツが制作できるのです。
開催内容も自ずと決まり、制作に携わるスタッフの負担も軽減されるでしょう。ウェビナー前のアンケートは、『参加申し込みフォーム』に質問を付け加える形になります。
セミナー終了直後に依頼
ウェビナー後のアンケートでは、講義内容に対する参加者の生の声が収集できます。後日、参加のお礼を兼ねてメールでアンケートを取る方法もありますが、時間が経つにつれて印象が薄れるため、終了直後に実施するのが理想です。
「スライドの文字が小さすぎた」「講師の話が早口でついていけなかった」といったマイナスの評価は次回のウェビナーに反映しましょう。
後日、メールでアンケートを取る際はウェビナー録画の視聴URLを共有したり、有益な情報を提供したりして、何らかのインセンティブを付与するのがポイントです。
投票機能を使ってセミナーの途中も
途中にアンケートを取るメリットは、参加者の声がリアルタイムに収集できることです。ウェビナー終了直前に退席をする人も多いため、話が半分ほど進んだ時点でアンケートを実施しましょう。
ただし、タイミングを誤ると参加者の集中力が途切れ、途中離脱につながることが懸念されます。休憩時間を設けている場合は、後半のウェビナーが始まる前にアンケートを行うのが賢明です。
Zoomビデオウェビナーには『投票機能』があり、ウェビナーの最中に『単一回答』または『多項目選択式』の投票が実施できます。統計や視聴者の理解度測定などに活用しましょう。
オンラインでも回答率が高いアンケートとは
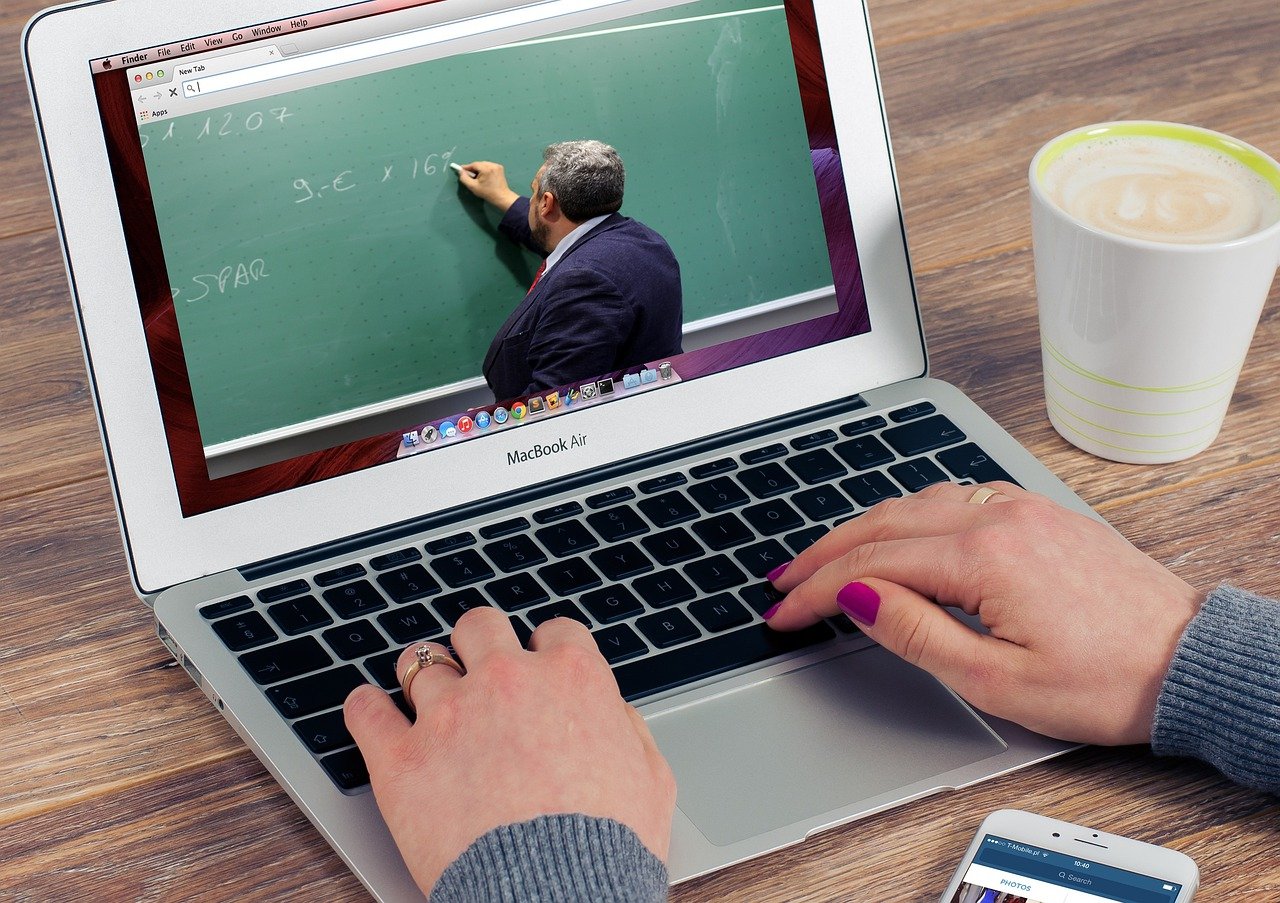
(出典) pixabay.com[/caption]
アンケートの回答率が低いときは、参加者の立場に立ち「回答率が下がるのはなぜか?」を考えてみる必要があるでしょう。非対面においては、利用目的が不明で、かつ回答に時間が掛かるンケートは敬遠されてしまいます。
個人情報の利用範囲、目的を記載する
多くの利用者は、オンライン上での『個人情報の取り扱い』に不安を抱いています。アンケートで個人情報を取得する際は、必ず『プライバシーポリシー』を提示しましょう。
プライバシーポリシーは『個人情報保護方針』とも呼ばれ、サイト上で収集した個人情報の利用範囲や目的を定めた方針です。「公表している以外の用途で個人情報は利用しません」と明言していることになるため、参加者は安心して回答ができます。
『プライバシーポリシーに同意する』というチェック項目を用意しておくと、参加者が目を通したかどうか分かるでしょう。
選択式と自由記述式はバランス良く
アンケートの形式は、『選択式』と『自由記述式』に大別されます。質問の内容に応じて、両方を使い分けましょう。
選択式は、 事前に準備された回答から単一または複数の答えを選ぶ方式です。回答に時間が掛からないため、回答率が上がりやすい傾向があります。集計がしやすく、正確なデータによる『統計的な解析』に活用できるでしょう。
ただ、答えが用意されている分、想定内の回答しか得られないのはデメリットです。
その点、自由記述式は参加者のありのままの声をくみ上げることができ、思いもよらぬアイデアや解決法が見つかる可能性が高いでしょう。自由記述式ばかりを並べると参加者の負担になってしまうため、1、2カ所にとどめるのがベターです。
アンケートの内容

(出典) unsplash.com[/caption]
アンケートの回答は今後のウェビナーや営業活動における重要な資料です。アンケートの目的を明確にした上で、目的を達成するために必要な設問を設定しましょう。
参加者についての質問
アンケートで欠かせないのが、参加者の『属性』に関する質問です。属性ごとの特徴や傾向が分かれば、ペルソナを的確に捉えた効果の高いアプローチが可能となります。
- 名前
- 連絡先
- 住所
- 性別
- 婚姻状況
- 家族構成
- 職業・業種・会社名
- 年収
氏名や連絡先はフォームに入力してもらう必要がありますが、そのほかは回答が容易な『チェックボックス』や『ドロップダウンメニュー』を活用します。
属性は、コンテンツ制作においても重要な材料となるため、ウェビナー開催前の『参加申し込みフォーム』で収集するのが良いでしょう。
ウェビナーに参加した目的
ウェビナーに参加する目的や動機は人によってさまざまです。
「業務に役立つ知識やスキルを身に付けたい」という人もいれば、「世の中のトレンドを把握したい」という人もいます。「SNSで偶然目に入ったから参加しただけ」という人もいるでしょう。
目的や動機を調査することで、『参加者がウェビナーに求めていること』や『どんなニーズを持った層が集まっているのか』が明らかになります。
自由記述形式の方が本音は反映されやすいですが、言語化が苦手な人は面倒に感じてしまう可能性があります。回答率の低下が見られた場合は、選択式で『その他』を選んだ場合にのみ記述してもらうのも良いでしょう。
ウェビナーに満足していただけたか
ウェビナー終了後のアンケートには、ウェビナーの感想や受講後の変化、満足度に関する質問を設けます。
『ウェビナーには満足しましたか?』『目的にかなう情報や知識は得られましたか?』といったように満足度を二者択一式で質問した後、記述式で『理由』を述べてもらいましょう。
『満足した』と答えた人は、自社が提供するサービスとニーズが一致している見込み客です。相手に合ったアプローチをすれば、顧客化する可能性は高いでしょう。
『満足できなかった』という回答があれば、ウェビナーの内容やアプローチの仕方を根本的に見直す必要があります。
特に聞きたい項目は上部に
アンケートは下に行くほど回答率が下がります。重要な質問はアンケートの序盤に入れ、徐々に優先順位が下がる形にするのが基本です。必ず聞きたい質問には『回答必須項目』の印を入れておきましょう。
また、YES・NOで答えられる簡単な設問は上位に、自分の意見や考えをまとめる必要がある設問は下位に設定する配慮も忘れてはいけません。1番最初に記述式の面倒な設問があると、回答する気持ちが失せてしまいます。
Zoomアンケートの作り方
Zoomビデオウェビナーでは、アンケートの事前予約が可能です。回答はレポートにできるため、集計の手間が掛かりません。
アンケートを作成するには、Zoomウェブポータルにサインイン後、『ウェビナー』のタブをクリックします。アンケートを追加するウェビナーを選択し、画面下部の『投票/アンケート』→『+アンケートの新規作成』より内容を編集しましょう。
出席者がアンケートを受ける方法は、『ウェビナー終了時にブラウザに表示する』と『フォローアップメールにリンクを表示する』の2パターンです。『アンケートの表示方法』の横にある『設定の編集』より、いずれかの方法を選択しましょう。
ツールのアンケート機能のメリット、デメリット

(出典) unsplash.com[/caption]
ウェビナーのアンケートは、『ウェビナーツールのアンケート機能を使う方法』と『外部サービスを導入する方法』の二つの選択肢があります。ツールのアンケート機能を使う場合、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?
扱い慣れたツール内で作成できる
国内で提供されている大半のウェビナーツールには『アンケート機能』があります。以下はアンケート機能があるツールの一例です。
- Zoomビデオウェビナー
- V-CUBEセミナー
- Cisco Webex Events
- GigaCast
- ネクプロ
- LiveOn
- Calling Webinar
- Microsoft Teams
アンケート機能のメリットは、使い慣れたツールで簡単にアンケートが作成できることです。一部のツールにはアンケートの『レポート作成機能』があり、配信からアンケートの集計作業までが一つのツール内で完結します。
アンケート機能や投票機能は、ウェビナーツールの『基本的な機能』に含まれるため、別料金が発生しないケースが大半です。
ツールによってはアンケート機能がない
アンケート機能は全てのウェビナーツールに搭載されているわけではありません。アンケート機能が付いていても、回答形式が決まっていたり、自由にカスタマイズができなかったりして、思いどおりのアンケートが作成できないケースもあります。
アンケート機能に限らず、無料のツールや格安ツールは機能がそれほど充実していません。導入時は複数のツールを比較し、使いにくいところはないか、不足している機能はないかを十分にチェックしましょう。
外部サービスのメリット、デメリット

(出典) pixabay.com[/caption]
ウェビナーツールにアンケート機能がない場合は、外部のアンケートサービスを利用するのが一般的です。ツールを変えても同じアンケートフォームが使い続けられるため、使い勝手が良いと感じる人もいるようです。
誰でも利用できる
外部のアンケートサービスは、『無料』と『有料』の2種類があります。誰でも利用ができる上、さまざまな用途に使えるのがメリットでしょう。
アンケート専用ツールなので、選択肢・プルダウン形式・評価スケールなどの複数の形式に対応しています。テンプレートが豊富で、イメージどおりのアンケートに仕上がりやすいのも利点です。
- Googleフォーム
- Microsoft Forms
- ミルトーク
- Questant
- formrun
- SurveyMonkey
- CustomForm
集計の手間などがデメリット
外部のアンケートサービスはウェビナーツールと連携ができないため、アンケートの誘導や集計に手間が掛かるのがデメリットです。
参加者をアンケートに誘導するには、ウェビナーのチャットまたはメールアドレスにアンケート画面のURLを貼り付けて送信する形になります。
Zoomビデオウェビナーでは、ウェビナーの『投票/アンケート』にある『+サードパーティのアンケートを使用する』をクリックして、アンケートフォームのURLを入力します。
ツールのアンケート機能は、どの参加者がどんな回答をしたのかがすぐに分かりますが、外部のアンケートサービスでは、回答と参加者の名前を突き合わせ、集計する作業が必要です。
アンケート後に行うこと

(出典) pexels.com[/caption]
アンケート回収後は、顧客のニーズを把握した上で、適切なフォローアップを行いましょう。『アンケート結果の分析』と『お礼のメール』の重要性について解説します。
お礼メールの送信
アンケート後、一人一人に『お礼のメール』を送ると、参加者との間に信頼関係が構築されます。
アンケートサービスの中には、『自動返信機能』が付いたものがありますが、顧客につながりそうな見込み客に対しては、画一的な定型文ではなく、『個別のメッセージ』を作成する方が良いでしょう。
セミナーへの参加とアンケート回答に謝意を示すと共に、次回のセミナーのスケジュールや業界の最新情報、自社サービスの紹介など、次のアクションにつながるような情報を加えるのがポイントです。
結果を分析する
アンケートは集計と分析がもっとも重要なプロセスです。分析にはいくつかの方法がありますが、『単純集計』で全体像を把握した後、『クロス集計』でデータを深掘りしていくのが一般的です。
クロス集計では、『40代×独身×設問』といったように、二つ以上の項目を掛け合わせていきます。ほかのデータと照らし合わせることで、そのセグメントに共通する特徴や傾向を探り出すことが可能です。
アンケート分析の目的は、顧客のニーズや現在の課題を可視化することです。分析結果を基に、今後の戦略を立てていきましょう。
参加者への連絡のポイント

(出典) pixabay.com[/caption]
ウェビナーが盛況に終わっても、自らアクションを起こす参加者はごく一握りです。主催側のフォローアップ体制が整っていなければ、何度ウェビナーを開催しても思うような結果は得られません。積極的にフォローし、相手に好印象を与えましょう。
アンケート結果を抜粋して報告する
ウェビナー後のメールでは、ウェビナー参加やアンケート回答へのお礼を述べると共に、集計した『アンケート結果』を抜粋して報告します。
選択式の回答は、円グラフや表を使って視覚的に分かりやすく表示し、自由記述式の『感想』や『改善点』は、簡単に要約して箇条書きで掲載しましょう。最後に、アンケート結果に対する主催側の感想や今後の予定を加えます。
アンケート結果によって、参加者は自分がどのような立ち位置や状況にいるのかが把握できます。データを提供した回答者は、「アンケート結果が正しく活用されている」という安心感を覚えるでしょう。
資料や動画の送付も効果的
後日、メールにてアンケートを依頼する場合は、回答率の低下を防ぐために『インセンティブ』を提示します。
ポイントのような金銭的価値のあるものが望ましいですが、予算的に余裕がない場合は、『セミナー録画』や『オリジナル資料』などを送付しましょう。ライブ配信中に回答しきれなかった質問を『Q&A集』にまとめてプレゼントするのもおすすめです。
『自動返信フォーム』を使って録画や資料の送付を行えば、担当者の負担が軽減されます。
動画はコンテンツとしても活用できる
セミナー録画は、アンケート回答者への特典としてだけでなく、有料・無料の『コンテンツ』としても活用が可能です。
自社の公式サイトやSNSなどにアップすれば、ライブ配信を見逃してしまった人や、セミナーの存在を知らなかった人の目にも触れることになるでしょう。
近年は、コンテンツの掲載先として『Webinar Room』が活用されています。さまざまな企業のウェビナーが無料で視聴できるポータルサイトで、最新情報を効率良くキャッチアップしたいビジネスパーソンに人気があります。
企業は、定期的にコンテンツをアップすることで、ハウスリスト以外の視聴ユーザー情報を継続的に取得することが可能です。初期費用や掲載費用が掛からないため、コストも最小限に抑えられます。公式サイトで詳しい資料を請求しましょう。
【公式】Webinar Room | 無料でセミナー動画が見放題まとめ
アンケートの目的は企業によってさまざまですが、ウェビナーのアンケートは『今後の課題』や『顧客のニーズ』を見つけるために行うのが一般的です。
ダラダラと長い設問は回答率の低下を招きます。回答者にできるだけ負担を掛けないように、シンプルで分かりやすい設問を設定しましょう。アンケートに協力してもらえそうにない場合は、『インセンティブ』を付与するのが有効です。








