ウェビナーノウハウ
ウェビナー開催までの流れ。予定の立て方と事前準備のポイント
最終更新日:2022/06/28
ウェビナー開催には、参加人数や内容にマッチしたウェビナーツールや機材が必要です。『ペルソナ』や『開催目的』を明確にした上で、参加者の立場に立ったコンテンツ制作を進めましょう。ウェビナーを成功させるコツや開催までの準備の流れを解説します。
目次
ウェビナーの魅力

(出典) unsplash.com[/caption]
ウェビナーとは、インターネット(ウェブ)を活用して行う『オンラインセミナー』のことです。大人数のセミナーが非対面できることから、対面式セミナーからウェビナーへと移行する企業が増えています。
『集客』『コスト』『準備』の三つの視点から見たウェビナーの魅力を紹介します。
場所を選ばず集客が可能
ウェビナーは、ZoomやCisco Webex Events、Cocripoなどの『ウェビナーツール』を用いて開催され、参加者はPCやタブレット、スマホを使って視聴します。
ウェビナーの利点の一つに、『広範囲での集客が可能なこと』が挙げられます。場所の制限を受けないため、日本国内はもちろん、海外からの参加も見込めるでしょう。
対面式のセミナーを開催する場合、最初に『開催場所』を決めなければなりません。東京が会場であれば、地方に住む人のハードルが高くなり、「交通費がかかる」「移動時間が長い」などで参加を断念せざるを得ない人が出てきます。
会場費や人件費を抑えられる
二つ目のメリットは、セミナーにかかるコストが大幅に削減できることです。
対面式のセミナーを行う場合、『会場費』や運営スタッフの『人件費』がかかります。講師を招く場合は、講演料のほかに『ホテル代』や『交通費』も必要でしょう。
ウェビナー配信は、オフィスまたは専用スタジオを借りて行います。撮影をする機材やセッティングに多少の費用はかかりますが、対面式のセミナーに比べて大幅なコストダウンが可能です。
『ウェビナーツール』には、参加者の出席確認ができる機能やアンケート機能が搭載されており、受付やアンケート回収のための運営スタッフをわざわざ雇う必要がありません。画面上で資料を共有すれば、印刷費も削減できるでしょう。
カメラ、配信環境などがそろえば開催できる
開催が可能です。コストが低い上に準備に手間が掛からず、「限られた予算内で質の良いコンテンツを配信したい」という企業には最適といえます。
- PC(マイク・カメラ内蔵)または外付けのWebカメラ・マイク
- ウェビナーツール
- インターネット
『ウェビナーツール』は、接続可能人数や搭載機能などによって料金プランが変わります。人数や開催頻度を事前に決めた上でツールを選択しましょう。
視聴者は普段使用しているPCやスマホ、タブレットを使用して視聴します。PC以外の端末では『専用アプリ』が必要なケースがありますが、それ以外に準備するものはありません。
ウェビナーの開催目的を整理しよう

(出典) pexels.com[/caption]
企業では、商品のプロモーションや、自社サービスの説明会などにウェビナーを活用するケースが多いようです。ウェビナーの開催目的やペルソナを明らかにした上で、画面構成やスライドの内容を考えていきましょう。
ペルソナを設定する
ウェビナーの企画においては、『ペルソナ設定』が最初のステップです。ペルソナはマーケティング用語の一種で、サービスの対象となる人物像を指します。
『ターゲット』と同義ですが、よりリアリティのある『個人像』に落とし込んでいく点がターゲットとの違いです。
具体的には、年齢・性別・居住エリアだけでなく、家族構成や趣味、職業までに絞り込み「どんな人物に向けてセミナーを開催したいか」を明確にしていきます。
ペルソナを設定すると顧客ニーズが明確になり、より心に深く刺さるセミナーが企画できます。逆に、ペルソナが曖昧になると訴求力が弱まり、どの層にも響かないものとなってしまうでしょう。
目標を設定する
ウェビナー集客を行うにあたり、『目的』を明確にしましょう。ウェビナーを通して自社の商品やサービスの魅力を知ってもらいたいと考える企業は多いですが、ただ単に魅力を伝えるだけでは不十分です。
誰に何を伝え、最終的にどうなって欲しいかまでをしっかりとイメージしましょう。ポイントは『6W2H』に当てはめて目標を設定することです。
- Why(なぜ):目的
- When(いつ):開催日時・時間
- Where(どこで):開催場所
- Who(誰が):責任者や協力者
- Whom(誰に):参加者
- What(何を):コンテンツの内容
- How(どのように):目標達成のための具体的な道筋
- How much(どれだけ):予算
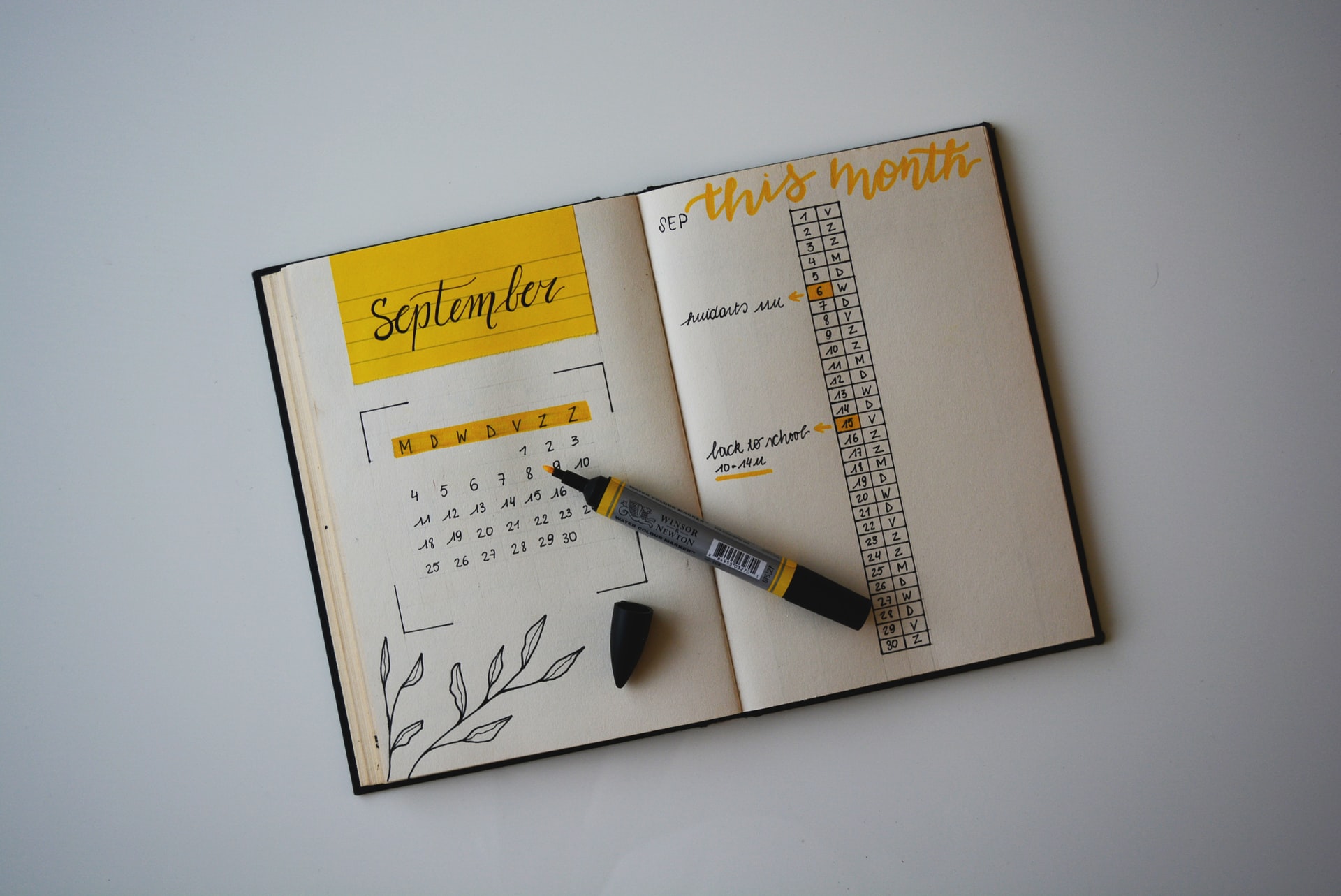
(出典) unsplash.com[/caption]
ウェビナー開催の最大の課題ともいえるのが、『集客』です。参加者の立場に立ち、適切な開催日時を設定するだけで集客率はグンとアップします。集客だけでなく、集めた参加者を途中退席させない工夫も考えましょう。
開催日、開催時間を決める
ウェビナーに参加しやすい時間帯や曜日は、参加対象の年齢・性別・職業・家族構成などによって異なります。
全体傾向としては、仕事や家事が一段落する『平日の20~22時』や、『土日の14~16時』が比較的参加しやすい時間帯といわれています。
ただ、連休の初日や行楽シーズンの土日は外出する人が増え、集客率が大きくダウンする可能性がある点に注意しましょう。
社会人を対象とするのであれば、『就業時間』や仕事が立て込みやすい『月曜日』、夜に予定が入りやすい『金曜日』は避けるのがベターです。
短時間のウェビナーを繰り返し開催したり、参加者にアンケートを取ったりして、参加率が高い時間帯・曜日を模索していきましょう。
視聴時間は長すぎない程度にする
1時間以上のウェビナーは参加者の集中力が落ちやすく、途中で退席する人が増加します。逆に、時間が短すぎると「聞く価値があるのだろうか」と迷う人が増えるようです。
ウェビナーの所要時間は30分~1時間を目安としましょう。1時間に設定した場合は、オープニング10分、講演30~40分、質疑応答10~20分といったように、参加者を飽きさせない構成を考えます。
設定に手間取る人や、仕事が長引いて開始時間に間に合わない人が一定数いることを考慮し、10分程度のオープニングを設けるのが親切です。
選択するウェビナーツールによっては、1回あたりの配信時間に制限があるため、オーバーしないような時間配分にしましょう。
途中離脱しやすいため他にも工夫が必要
ウェビナーは気軽に参加ができる半面、『途中離脱』が多くなりやすいのがデメリットです。内容がつまらないとそのまま退席してしまったり、ラジオ代わりにしてほかの作業を始めてしまったりする人もいます。
ウェビナーにはオンデマンド配信(録画配信)とライブ配信の2パターンがありますが、途中離脱が多いのはどちらも同じようです。その点、対面式セミナーは途中で席を立つと目立ってしまうため、なかなか退席ができません。
『集客しやすいが離脱もしやすい』というウェビナーの特徴を踏まえた上で、参加者・視聴者を飽きさせない工夫をすることが大切です。
視聴者の参加方法を決める

(出典) pexels.com[/caption]
ウェビナーへの参加方法は大きく二つあります。参加者目線での『参加のしやすさ』も重要ですが、見込み客の獲得やデータ管理の側面からも適切な参加方法を選ぶ必要があります。
事前登録制か、予約不要か
ウェビナーへの参加方法は、『事前登録制』と『予約不要』の2パターンがあります。事前登録制にするメリットは、主催者側が参加者情報や人数をあらかじめ把握できることです。
特に、開催の目的が『見込み客の獲得』である場合は事前登録制にするのがベストでしょう。ペルソナに合わせた適切な切り口でセミナーを進めていくことができます。
申し込みから視聴後のアンケート回答までを一つのツールで行うことで、顧客管理やデータ分析が容易になるでしょう。
参加費が無料で、かつ予約が不要の場合、参加枠がすぐに埋まる可能性があります。参加者の立場からすれば、事前登録の方が「席が確保されている」という安心感があるようです。
視聴者からの質問、チャット機能の活用
講師が話をするだけの一方通行のセミナーは離脱率が上がります。シナリオには、参加者からの『質疑応答』の時間を盛り込みましょう。
大半のウェビナーツールには、主催者と参加者の『双方のコミュニケーション』をかなえるさまざまな機能が付帯しています。
例えば、Zoomビデオウェビナーには、出席者・ホスト・共同ホスト・パネリストがテキストで交流できる『チャット機能』があり、質疑応答やディスカッションなどに活用が可能です。セミナーが始まる前にチャットの利用ルールを説明しておきましょう。
チャット機能のほかにも、質疑応答ができる『Q&A機能』や、ウェビナー中に参加者が自分の意見を発言できる『挙手機能』などがあります。
セミナー開催の形式を決める

(出典) pixabay.com[/caption]
ウェビナーにはさまざまな形式があります。配信は『オンデマンド配信』と『ライブ配信』の2パターンで、セミナーの進め方には『スライド形式』や『講義形式』などがあります。複数のスタイルを組み合わせるのもよいでしょう。
オンデマンド配信、ライブ配信
ウェビナーの配信形式には、オンデマンド配信とライブ配信があります。
『オンデマンド配信』は、録画済みのセミナー動画を配信する方法です。主催者と参加者が直接交流できないのが難点ですが、任意の時間帯・曜日に視聴ができるため、忙しいビジネスパーソンや動画を繰り返し見たい人には最適です。
配信側には、収録後の編集によってコンテンツの完成度を高められるというメリットがあります。ライブ配信でアプローチできない顧客層との接触も可能となるでしょう。
『ライブ配信』は、撮った映像をリアルタイムで視聴者に配信する『生放送』と同等の手法です。主催者と参加者の交流により、対面式セミナーのような臨場感や一体感が味わえます。
参加者の反応が直に確認できるのもライブ配信の良さでしょう。
スライド形式、講義形式
ウェビナーの進め方は、スライド形式と講義形式に区別されます。
『スライド形式』は、PowerPointなどで作成した『スライド資料』を用いる方法です。日本語は『同音異義語』が多く、耳で聞いて意味を判別するのが難しいケースがあります。
専門用語が頻出するウェビナーでは、図・グラフ・写真などによる視覚的補足がないと、話についていけない参加者が続出するでしょう。
ただ、スライドを多用すると、『話し手の熱量』が伝わりにくくなるため、スライドとプレゼンの両方をバランスよく盛り込むことが重要です。
一方の『講義形式』は、話し手の言葉や表情がメインとなります。臨場感があり、アピールしたい内容が直に参加者に伝わるのがメリットです。難しい説明には『ホワイトボード』を活用するとよいでしょう。
一方通行、双方向
『一方通行型』は、主催者(講義者)のみが話をするスタイルを指します。主催者と参加者、参加者同士の交流はありません。
基本的に、オンデマンド配信は一方通行型です。参加者の質疑応答で話題がそれたり、時間がオーバーしたりすることがなく、主催者の意図通りに話が進みます。
配信する側はウェビナーを録画して配信サイトにアップするだけのため、工数が少なくて済むのもメリットです。
『双方向型』は、主催者と参加者のコミュニケーションを重視するスタイルです。ウェビナーツールに搭載された『チャット』『Q&A』『挙手』『投票』などの各種機能を活用するため、対面式に近いウェビナーが実現します
ウェビナー成功のための準備のポイント

(出典) pixabay.com[/caption]
ウェビナーには、開催内容や規模にあった機材やツールの準備が欠かせません。参加者の立場に立った分かりやすい資料やスライドを用意した上で、当日までにリハーサルを実施しましょう。
開催内容に合った機材、ツールを用意
ウェビナーはPCとPCに内蔵されたマイク及びカメラがあればすぐにでも始められますが、クオリティの高さにこだわるのであれば、専門機材の購入を検討しましょう。
- Webカメラ
- 単一方向マイク
- 有線LAN
- 三脚・照明器具・グリーンバック・スイッチャー
ウェビナーツール選びのポイントとしては、『提供元(国内・海外)』『料金プラン』『サービス内容』『サポートの充実度』などが挙げられます。
質の高いコンテンツで他社との差別化を図りたい場合は、企画・演出・配信をトータルコーディネートしてくれる会社を探しましょう。熟練スタッフ立ち合いのもとで配信が行えます。
目を引く、わかりやすい資料を用意
ウェビナーの資料は、見やすさを重視しましょう。スマホでの視聴も考慮し、1ページに文字を詰め込みすぎないようにするのがポイントです。
スライドを使う際は、『1スライド・1メッセージ』を意識しましょう。テキストだけでなく『図表』や『写真』を適度に入れることで、視覚的に分かりやすい内容に仕上がります。
対面式セミナーに比べ、ウェビナーは参加者の集中力が長続きしにくい傾向があります。アニメーションで変化を付けたり、色に意味を持たせたりして、途中離脱を防ぐ工夫が大事です。
商品など資料以外のものも映せるように
ウェビナー中は実際の商品や写真などを見せながら話を進めましょう。離脱者が多いウェビナーの特徴として、画面上の変化が乏しいことが挙げられます。
話し手の顔だけを延々と映すだけのウェビナーは参加者を飽きさせてしまうばかりか、商品やサービスの魅力が十分に伝わりません。
同様に、スライドだけ、アニメーションだけの画面からは主役である発信者の熱量が感じられず、内容が記憶に残らない可能性があるでしょう。
『スライド(資料)』『話し手』『商品』が交互に表れる変化に富んだウェビナーは、参加者の心を引きつけます。
開始時間前の待機画面をアレンジ
開始時刻より早めに入室した参加者のために、『待機画面』を準備しましょう。画面が真っ暗で無音の状態だと、参加者は「日時を間違えたのではないか?」と不安な気持ちになります。
ウェビナーが始まる10~15分前から、講師のプロフィールやウェビナーの概要などをBGMと共に流しておくと、参加者は心の準備ができるでしょう。
Zoomビデオウェビナーの待機室ではオリジナルの待機画面やBGMが使用できないため、参加者を会場に入室させてから、画面共有機能を使ってスライドを流す形となります。
成功のカギを握るのは入念な事前準備

(出典) unsplash.com[/caption]
録画はやり直しがききますが、ライブ配信は一発勝負です。『相手に伝わるウェビナー』にするためには、入念な事前準備やリハーサルが欠かせません。『画面越しは伝わりにくい』ということを念頭に、話す練習をしてみましょう。
リハーサルを行う
セミナーに手慣れた講師でも、ウェビナー前のリハーサルは必要です。実際にウェビナーで使うスライドやスクリプトを用意して、『模擬配信』をすることをおすすめします。
ウェビナーは対面式セミナーと違い、参加者の反応が見えにくいのがデメリットです。
一方的に進めて参加者を置き去りにしてしまったり、専門用語を多用して内容が分かりにくくなってしまったりというケースは珍しくありません。リハーサルでは以下のポイントもチェックしましょう。
- 時間配分
- 画面・音声
- スライドの見やすさ(文字の大きさ・情報量)
- サポートスタッフの役割分担
効果的な練習のやり方
相手を前にして話をするのと異なり、無反応なカメラの前では話し方がぎこちなくなってしまいます。
リハーサルでは、カメラの奥に『聞き役』を配置して、その相手に向かって話をするのも一つの手です。頷いて話を聞いてくれる相手がいると、表情が豊かになり、声にハリが出るようになります。
画面越しは、表情や声の抑揚が伝わりにくいため、『ジェスチャー』を交えながら話をするのもよいでしょう。音声情報に手の動きが加わると、聞き手はより内容を理解しやすくなります。
ウェビナー開催後にすること

(出典) pexels.com[/caption]
ウェビナーで思うように効果が上がらない企業は、『ウェビナー後のフォロー』をなおざりにしている傾向があります。『ライブ配信をしたら終わり』ではなく、アーカイブ配信で継続的にリードを獲得しましょう。
アンケートや連絡をしてフォローする
企業がウェビナーやセミナーを開催するのは、『見込み客』を獲得するためです。対面式のセミナーでは、セミナー終了後にアンケート用紙を回収したり、ブースを設けて個別相談会を実施したりして、フォローを行います。
ウェビナーでは、対面型のような直接的なフォローはできませんが、ツールに搭載されている『アンケート機能』を活用すれば、参加者の声を吸い上げることが可能です。
参加申し込み時に参加者のメールアドレスを取得していた場合は、『フォローメール』を送り、参加者との関係性を築きましょう。
録画して参加者に共有する場合
ウェビナー後は、参加者や参加できなかった人に対して、『録画』を共有しましょう。録画は、自由にリピート再生ができるため、内容がより深く理解できるのがメリットです。
Zoomビデオウェビナーの場合、録画の保存先が『クラウド』と『ローカル』から選べます。クラウド保存した録画を他人と共有するときは、クラウドにアクセスするURLを相手に通知するだけでOKです。
より多くの人に録画を共有したい場合は、ウェビナー視聴サイト『Webinar Room』に録画をアップするのもよいでしょう。完全報酬型で、初期費用や掲載費用は一切かかりません。
【公式】Webinar Room | 無料でセミナー動画が見放題アーカイブ配信でリード獲得
多くの企業はウェビナーを商品・サービスのプロモーションの場として活用しています。しかし、ライブ配信を単発で行うだけでは効果が少なく、当日参加できなかった見込み客や潜在顧客を逃してしまう可能性が高いでしょう。
『アーカイブ配信』により『いつでも自由に視聴できるコンテンツ』にしておくことで、継続的なリード獲得が可能になります。
新たな顧客とのタッチポイントとして活用したいのが、『Webinar Room』です。企業の最新ウェビナーを集約した配信プラットフォームで、ユーザーが録画を視聴すると、企業側にユーザー情報が送信される仕組みです。
ウェビナーのたびにWebinar Roomに録画をアップすれば、継続的なリード獲得につながるでしょう。企業向けの詳しい資料は公式サイトのフォームから請求できます。
【公式】Webinar Room | 無料でセミナー動画が見放題まとめ
非対面で大規模な集客が行えるウェビナーは企業にとって多くのメリットがありますが、「思うように集客ができない」「集客できても離脱率が高い」といった声も多く聞かれます。
集客時はウェビナー開催の目的やペルソナを明確にした上で内容を構成しましょう。離脱率が高いことを踏まえ、スライドや時間配分にも工夫が必要です。








